究極の抽象美

東京が梅雨入りした6月10日の午後に菅野沖彦氏の最新サウンドを聴かせていただいた。
・
半透明の微細なグラデーションを持つ花弁のひとひらが天から舞い降り、やがて薄い空気の層をはさんで幾重にも重なっていく。そして気がつくとそれらは跡形もなく消え去っている。このコンマ何秒かの艶やかで儚い一瞬の「美」。それでいながら限界を感じさせない咆哮のダイナミズム。これらがシームレスに存在している。
・・・一昨年の夏、菅野邸に伺い、初めて耳にしたその音は事前に想像していたものと異なっていた。ゴージャスなアメリカンサウンドというぼくの単細胞的先入観はものの見事に打ち砕かれた。

・
黄金時代のJBLユニットを用いたオリジナルシステムもマッキントッシュのXRTも、まったく同質のクオリティにまで追い込む「技」をもって、GermanPhysiksのDDDを組み込むのだから興味は尽きない。
空間に展開するサウンドスペクトラムは従来のものと変わるわけではなかったが、一聴して分かるのは躍動する生命感と色価(Valoir)の幅だ。チタンの薄膜を波及的に振動させ、全方位に放射するDDD。意外にもホーンスピーカに似た浸透力をもっているようだ。氏はこの帯域の上にELAC
4PI PLUS.2を加えているので、すべてがDDDの成果とは言えないまでも、変換器から生み出されるサウンドとしては未踏の領域ではないかと思った。
・
シベリウス「レミンカイネン」サラステ指揮、トロント交響楽団。リスニングエリアに充満するライブネスはコンサートホールのそれを突き抜け、演奏者の衝動・動機や作曲家の原初的イメージさえ伺えるような次元と言えばよいのか。空間に音が在るのではなく、音に内在するベクトルをもって空間を構築する2CHステレオの凄さを改めて思った。
・
そして圧巻はミハエル・プレトニョフのシューマン「交響的練習曲」。ハンマーフェルトが絃に当たる瞬間のためらい感に始まり、その後の直角に切り立つエッジ(*
輪郭のことではなく)そして巻き線のうねりと濁り感・・・。グランドピアノのあの匂いを漂わせながら、黒く底光りするボディ、放射される音の力・・・。
・
 鍛え上げたプロの技とアマチュアのようにときめく情熱の総体が、菅野氏のオーディオワールドだ。「仕事」で括られる範疇とは無縁の入魂のライフワーク。「機械が変わったから音が変わる」という受動的なレベルから遠く離れた、究極の表現装置。テクノロジーが拡張する新たな地平を呑み込み、自らの表現に至らしめる様はスリリングでさえある。 鍛え上げたプロの技とアマチュアのようにときめく情熱の総体が、菅野氏のオーディオワールドだ。「仕事」で括られる範疇とは無縁の入魂のライフワーク。「機械が変わったから音が変わる」という受動的なレベルから遠く離れた、究極の表現装置。テクノロジーが拡張する新たな地平を呑み込み、自らの表現に至らしめる様はスリリングでさえある。
・
持参したCDを1枚だけかけてもらった。アマリア・ロドリゲスが1945年にリオデジャネイロで録音したSP復刻盤から「Troca De
Olhares」。当然ながら超ナローレンジであり最新のオーディオ装置が苦手とするソースだ。こんなものを持って行くのは無礼かもしれないと思ったが、聴かせてもらうのはこれと決めていた。
・・・はるか60年の時空を飛び越えた圧倒的な実在感に、涙が出た。ぽっと浮かび上がる25歳のアマリア。艶やかで匂い立つような色彩感がこの空間に充満 し、滲み出る仄かな愁いが胸を打つ。実のところこのような音源は我が家の装置の得意科目であり、もしや(笑)とも考えていたのだが、菅野邸のアマリアは数段上を行くリアリティで、モノラルであることさえ忘れさせた。(2005年6月記) し、滲み出る仄かな愁いが胸を打つ。実のところこのような音源は我が家の装置の得意科目であり、もしや(笑)とも考えていたのだが、菅野邸のアマリアは数段上を行くリアリティで、モノラルであることさえ忘れさせた。(2005年6月記)
|
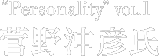


 鍛え上げたプロの技とアマチュアのようにときめく情熱の総体が、菅野氏のオーディオワールドだ。「仕事」で括られる範疇とは無縁の入魂のライフワーク。「機械が変わったから音が変わる」という受動的なレベルから遠く離れた、究極の表現装置。テクノロジーが拡張する新たな地平を呑み込み、自らの表現に至らしめる様はスリリングでさえある。
鍛え上げたプロの技とアマチュアのようにときめく情熱の総体が、菅野氏のオーディオワールドだ。「仕事」で括られる範疇とは無縁の入魂のライフワーク。「機械が変わったから音が変わる」という受動的なレベルから遠く離れた、究極の表現装置。テクノロジーが拡張する新たな地平を呑み込み、自らの表現に至らしめる様はスリリングでさえある。 し、滲み出る仄かな愁いが胸を打つ。実のところこのような音源は我が家の装置の得意科目であり、もしや(笑)とも考えていたのだが、菅野邸のアマリアは数段上を行くリアリティで、モノラルであることさえ忘れさせた。(2005年6月記)
し、滲み出る仄かな愁いが胸を打つ。実のところこのような音源は我が家の装置の得意科目であり、もしや(笑)とも考えていたのだが、菅野邸のアマリアは数段上を行くリアリティで、モノラルであることさえ忘れさせた。(2005年6月記)