| 2017/06/01 |
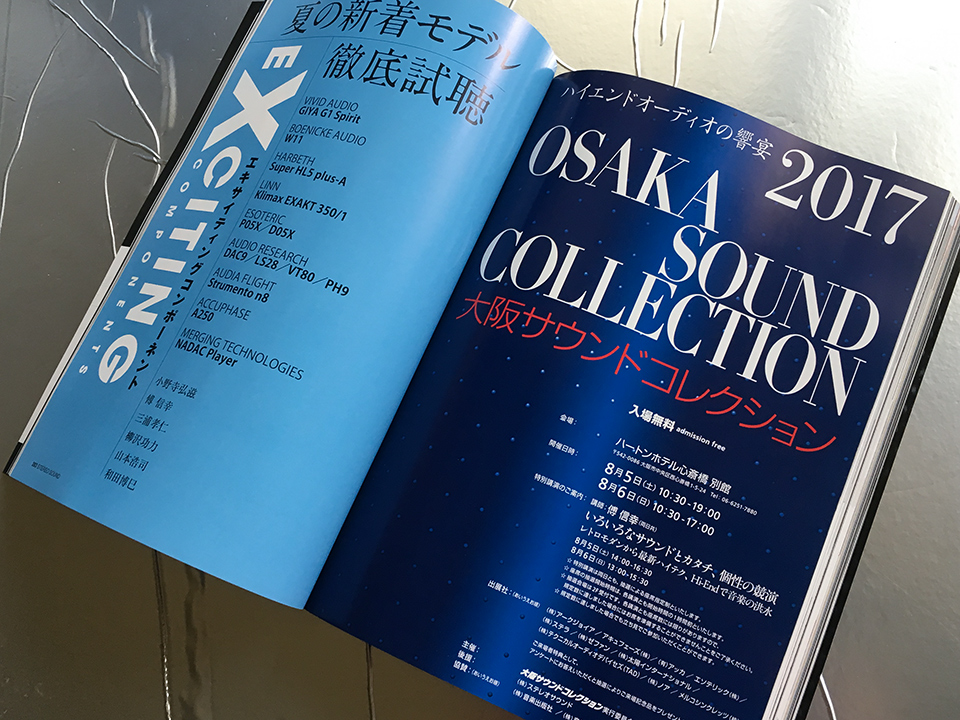 |
| 1992 担当して3年目。 |
| 2017/05/08 |
 |
| 1991 改憲論議よりも・・・ 現日本国憲法の前文における国家理念は、全世界が手本にすべき崇高な精神にみちているが、現実にそぐわないから変えるという論法は、現実が評価に値するレベルに到達し、古い条文に価値を見いだせない場合に限られるのではないだろうか。現実は下記のような惨状であり、そもそも法を遵守できない政権が法の大本である憲法を変更するなど、あってはならないことだ。真に求められるのは、アメリカ合衆国の属国であることを拒否し、本当の意味で「日本を取り戻す」ためのムーブメントだが、何十年レベルでは不可能なのだろうか。そのまえにフクイチの惨状が加速して日本消滅の可能性のほうが高いかもしれず、支配者たちはそこまで見越したうえでのシナリオなのだと疑っている。 日本国憲法前文の真相 「日本国民は、不正を疑われながら選挙される国会における代表者を通じて行動し、政治家と官僚を操るアメリカ合衆国政府およびその背後に控える巨大金融資本のために、わが国全土にわたつてもたらされた恵沢を確保し、ここに国家主権を放棄することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものではなく、その権威はアメリカ合衆国に由来し、その権力は日米合同委員会の代表者がこれを行使し、その福利を国民がこれを享受することは認められない。これは戦勝国普遍の原理であり、この国の現実は、かかる原理に基くものである。」(以下略) ここで、大いに共感したコラムをご紹介したい。 「そもそも 日本人は自分の運命を自分で決めたことがあるのだろうか」反戦な家づくり より http://sensouhantai.blog25.fc2.com/blog-entry-1643.html iPhone 6s f:2.2, 1/300sec, iso:25 |
| 2017/05/02 |
 |
| 1990 バックハウスのバッハ 一切の虚飾を排した無垢のバッハといえば良いのか。とはいえ堅苦しいものではなく、潤いのある音楽美にあふれた演奏だ。バックハウスのバッハで、残された録音がどのくらいあるのか知らないが、個人的にこの演奏がリファレンスなのだ。 |
| 2017/05/02 |
 |
| 1989 オスカー・ピーターソン MELLOW MOOD オスカー・ピーターソンは、ジャズピアノの入門向けといったポジションもあって、かくいう私も中学生のとき最初に求めたレコードがヴァーブのベスト盤だった訳だが、じつはもの凄いピアニストだ。 この「MELLOW MOOD」はMPSのオーナー邸でのプライベートライブという企画だが、けしてアットホームで穏やかな演奏ではなく、入魂の超絶パフォーマンスなのだ。H. Silverの"Nicas' Dream"では、地平線まで散りばめた無数のダイアモンドの一粒一粒が輝きを放ちながら息の長いフレーズに恍惚となること請け合いで、そのさまはルーレット盤「バド・パウエルの芸術」のなかの”インディアナ”に匹敵すると言ったら言い過ぎか? レーベルセンターのヒゲには注意しているのだが、Dualのオートチェンジャーの爪痕がしっかり付いている(笑)1968年録音、オスカー・ピーターソン(pf)、サム・ジョーンズ(b)、ボビー・ダーハム(ds) |
| 2017/04/26 |
| 1988 SPレコード三題(改訂) 調整から戻ってきたテクニクスSL-1200GAEによるSP盤再生。音のエジソンMC(3ミル針)と自家製フォノイコを使用。 iPhone6s によるエアー録画。 ドリス・デイ "Lost in Loveliness"(1954年) すでにLP盤と併売されていた時代と思われるがコンディションの良いSP盤はやはり凄い! 艶やかさがしっかり再現できている。 https://youtu.be/2W4nNGH2gKI 砂川捨丸+中村春代 "干支萬歳" 電気吹き込み初期の録音(1926年6月発売) 盤質は悪いが、私にとっては宝物。グイグイ迫るドライブ感に圧倒される。 https://youtu.be/KC3qxOcumT8 二人椀久 九世芳村伊四郎+稀音家六治 (1946年) 後の七世芳村伊十郎と山田抄太郎。全10面のうちから第3面、CD化されていない貴重な音源。 RIAAカーブ可変フォノイコライザーを使用。 https://youtu.be/Yx0EcbjoIJg |
| 2017/03/10 |
 |
| 1987 STEREO SOUND No.202 菅野沖彦氏が一線を退かれてから、骨太の巻頭言がなくなり寂しい想いがあったのは事実だが、今月発売のNo.202春号では興味深い3本の記事が巻頭に置かれ、かつてのクオリティマガジンの面影が少しだけ蘇った。 嶋譲氏の「サウンドステージの探求」は、素晴らしいオーディオ評論であると思う。歴史を俯瞰しつつも具体的事例(ディテール)が克明であり、ともすれば「音像」と「音場」に二分されていた過去の論議を統合する視点をもっている。オーディオ評論とは、機械・技術を介して音楽体験の質を問うこと、と考えている私にとって渇望していた記事だ。文章構成に関して、起・承・転(事例)で唐突に終わっているところに不自然さを感じた。これは短期集中連載を謳っているためなのだろうが、次回が3か月後ということを勘案すると、次号に繋げるべき「章まとめ」が欲しいところ。とはいえ、新登場の岡崎哲也氏のエッセイとともに次号が待ち遠しい。 ※写真は芦ノ湖上空、3月8日17時36分撮影。羊型の雲と鳥と飛行機! |
| 2017/03/10 |
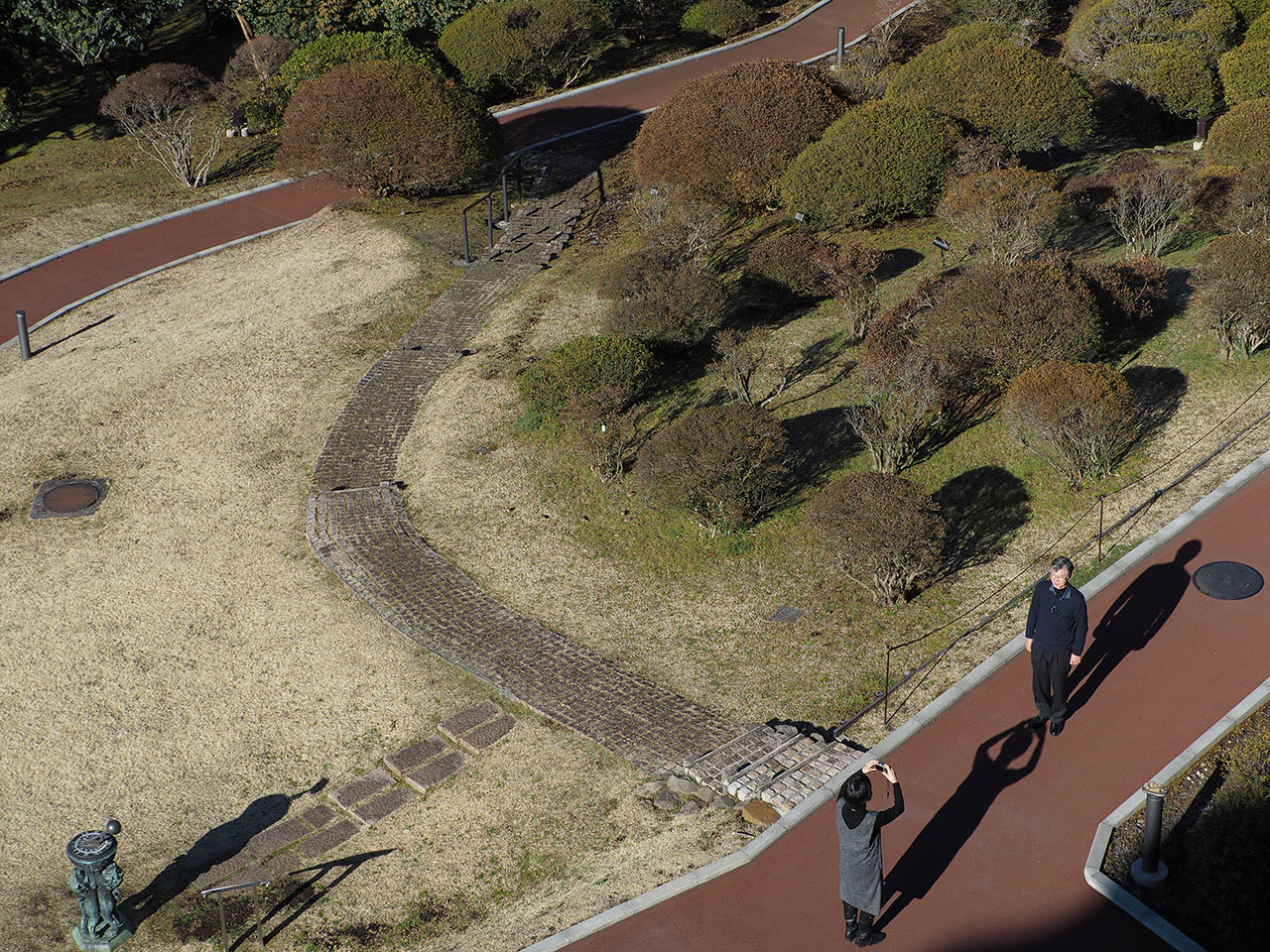 |
| 1986 |
| 2017/02/22 |
 |
| 1985 ベリンガーウルトラカーブ続報 ピンクノイズでRTA(リアルタイムアナライザー)を監視しながら、GEQのスライダーを調整していると、RTAが示すピーク/ディップ値とスライダーによる増減値にリニアな関連性がないということに気がつく。もとより定在波が理由のF特性の暴れは、空間での相互干渉であるため、音響出力の補整が裏目に出ることもある。例えばRTAで表示された−6dBのディップ帯域をスライダーで+6dB上げてもフラットにはならないことの方が多い。 ベリンガーウルトラカーブはデジタルソース専用で用いていたが、アナログソース用で使用しているGEQ(クラークテクニーク)の監視にウルトラカーブを用いリアルタイムでGEQ調整することで、好結果が得られた話は日記に書き忘れた。 デジタルソースでも、リアルタイム調整が出来れば効率的に的確な設定が可能なので、もう一台ということに相成った(笑) 写真上段のウルトラカーブはRTA専用で、ノンイコライジングのピンクノイズを下段のウルトラカーブに送り、こちらでGEQ操作を行う。この出力をマイテックデジタルDAコンバータを経由して、スピーカーから鳴らし、RTAのマイクロフォン入力に至る。 61バンドのRTAを見ながら、31バンドのGEQ操作なので、痒いところに手が届かないもどかしさもあるが、ごく短時間でこの程度まで追い込むことが可能だ。音質とDレンジの問題からフェーダーの操作幅を最大で6dB程度に制限している。写真のRTA画面は右CH、軸上1.2mでの一定時間アベレージを示している。横軸の点線は10dB単位なので、30Hzから15KHzまでこの枠内に収まっているようだ。あくまで、1/6oct帯域幅のなかの平均値ではあるが・・・ |


