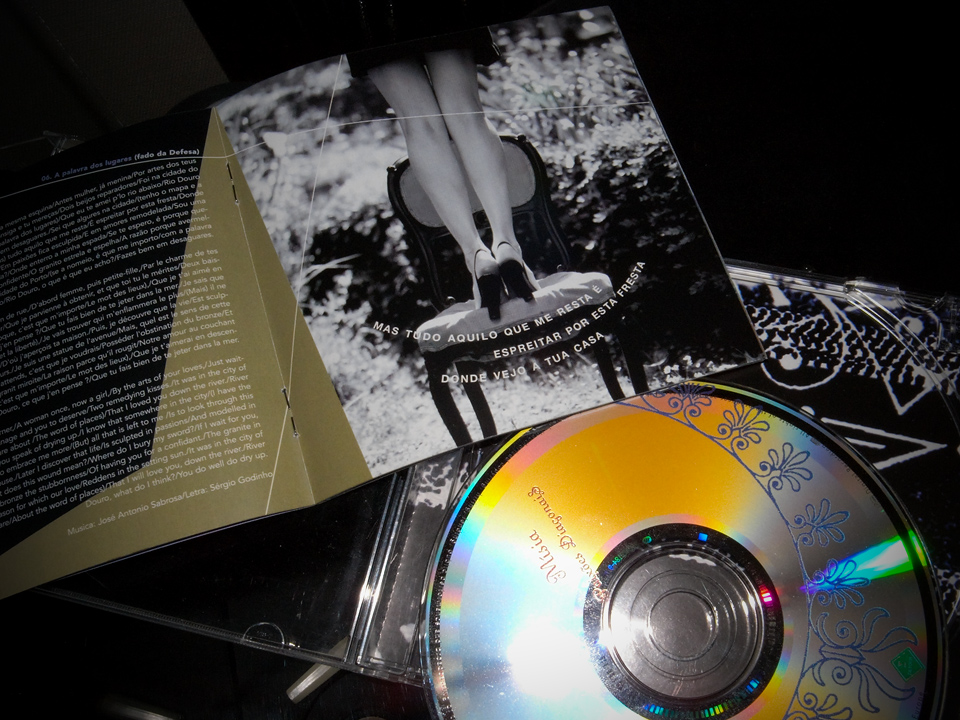1138 The Goldmund Media Room、究極の再現空間

壁面に埋め込まれた10CH+Center CHのスピーカー群。
3way構成のスピーカーユニットはそれぞれが専用パワーアンプと直結していて、スピーカーの至近にカスタマイズ "テロス" が総数で30基以上埋め込まれている。プログラムソースから帯域ディバイダ、パワーアンプ前段までは完全デジタル伝送であり、目指したのはリスニングポイントでの正確・厳密な周波数&位相制御だ。
打ち合わせのあと、ちょっとだけのつもりが延々2時間・・・
一人で居るのはもったいないような体験だった。
まず、マリア・ジョアン・ピリス「後期ショパン作品集」を聴く。
目の前はスピーカーさえ見えない漆黒の空間であるのに、ピリスがそこに存在している不思議さを思った。音の在処とはこの感覚のことかもしれない。
楽器の実在を超えて音楽そのものが立ちのぼるピリスの演奏ではあるが、グランドピアノとしては最高レベルの音響をその再生音から感じた。直角的エッジと緻密な質感、そしてしなやかで匂いたつ色香。菅野沖彦邸で体験したあのピアノの匂いを彷彿とさせる。
しかし、途方もない圧倒的Dレンジである。
持参したパコ・デ・ルシア「Luzia」では、これがいっそう顕著で、床を踏み抜くような強烈なサパテアドと弦に触れる微かなフィンガーノイズが同時に顕れる。こんなコントラストをかつて耳にしたことはない。常軌を逸した大音量だが、なるべく大きな音でとリクエストしたのだから仕方ない(笑)我が家のそれも大きいほうだが、そこからさらに+4.5dBくらいか。ゆうに120dBオーバーの世界だろう。耳の限界をすでに超えていたが、この再生空間のキャンバスにおいては破綻の兆しさえ伺えない。
ちなみにMedia Roomの最大設計音圧は130dB!である。
通常のオーディオ装置では、既成の部屋がまずあって、そこにスピーカーを置く。その空間は多様で、例えればスピーカーは荒海に出航する舟のように様々な障害に遭遇しながら、聴き手に音楽を届けているわけだ。その対処にオーディオの楽しみを見いだすことも重要ではあるが、音楽に辿り着くまでの膨大な時間を無駄と思う人、あるいはすべてをやり尽くし、さらに上があるのではと疑心暗鬼になったマニアetc...いずれのケースでもGoldmund Media Roomは最高のソリューションではないだろうか。ここでは、空間と出力ディバイスの完璧な整合性を求めるところから全体計画が成されている。
熱意あるオーディオファイル諸氏には、この成果をぜひ体験していただきたい。生演奏をいくら聴いても得られないオーディオの壮絶感覚というものは確実に存在し、そのイメージを拡張させる意味での貢献度は想像以上に高いはずだ。
※ステレオサウンド誌2009/SummerにMedia Roomの見開き広告が掲載されているので、こちらもご覧いただければ幸いです。
この稿は、ステラヴォックスジャパン(株)様の承諾を得て公開させていただきました。 |